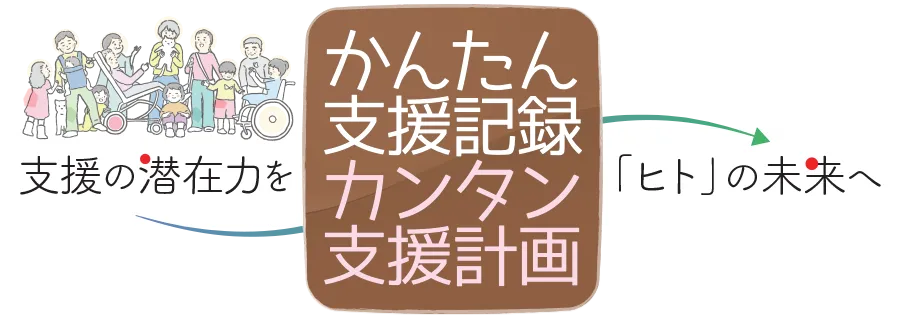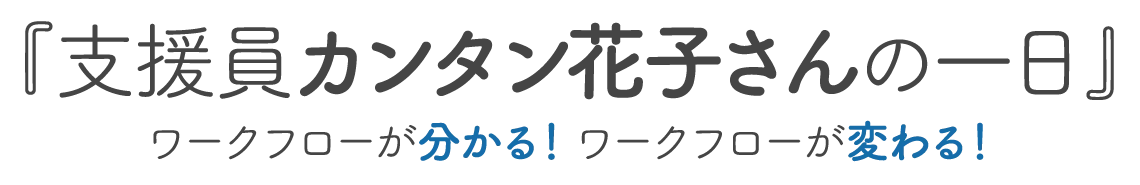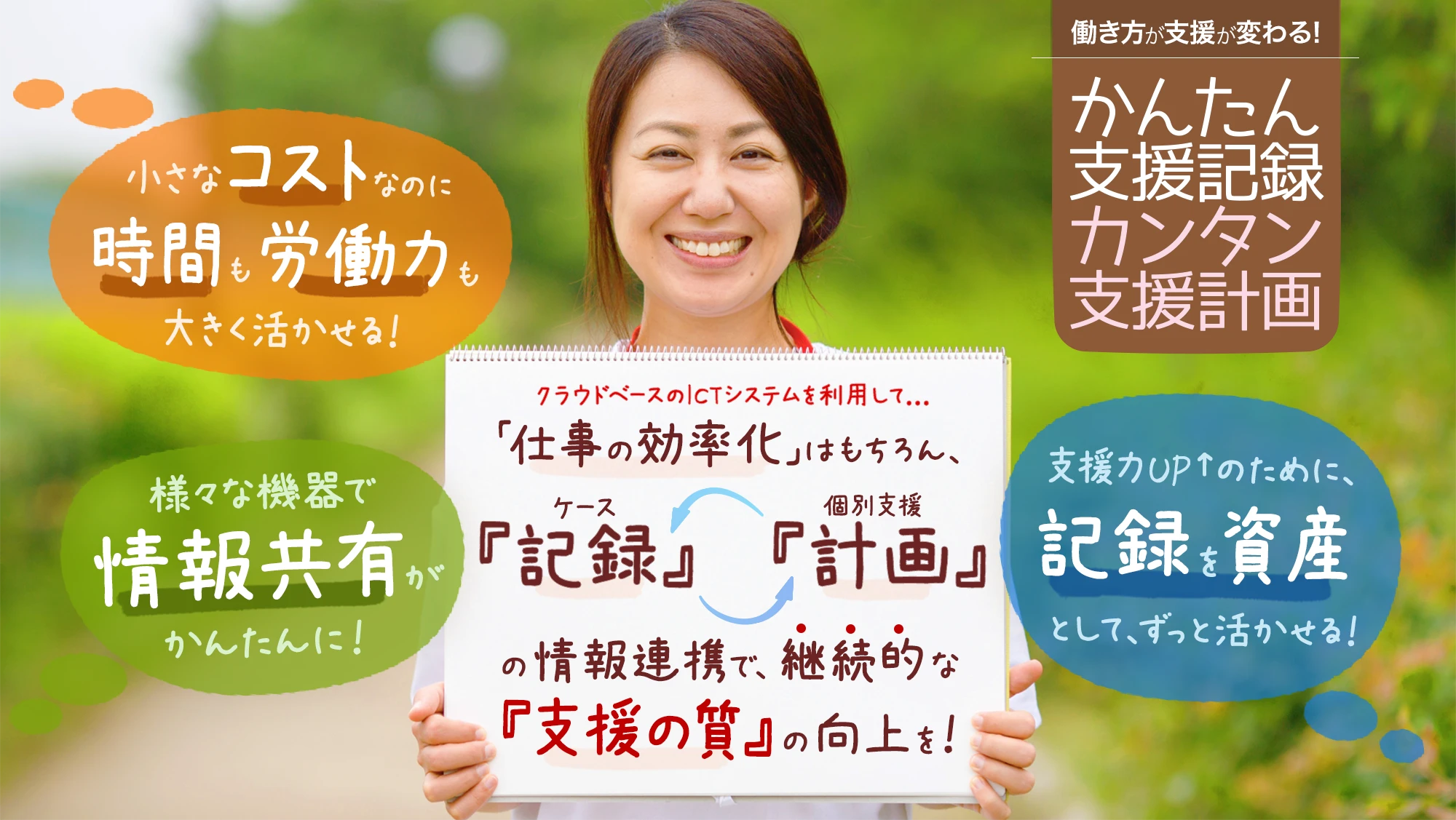ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その2
目次

福祉現場における記録の本質は、単なる業務の報告ではなく「支援の質を向上させるための資産となる」点にあります。この貴重なデータを最大限に引き出し、効率的かつ低コストで活用可能な基盤として整備できるのが、クラウド型記録システム「かんたん支援記録カンタン支援計画」です。
しかし、どれだけ優れたシステムが整っていても、「どのように書くべきか」という記録に盛り込むべき重要な要素を理解していなければ、現場で本当の意味で活かすことはできません。
前回は、『相談援助職の記録の書き方―短時間で適切な内容を表現するテクニック』という書籍を参考に、ケース記録( ≒ 支援記録・サービス提供記録・経過記録 )の目的や、記録の歴史的背景について要約しました。
今回はその続きとして、現場の支援者がどのような視点でケース記録を記入するべきかについての具体的な記載ポイントを分かりやすく紹介していきます。
ケース記録の記入時には、「利用者様毎の個別テンプレート」や「選択式テンプレート」など、各種テンプレート機能も活用して、記録時の「精度」と「効率」を上げることができます!
それでは、「支援の質の向上」に活かせる記録の書き方について、いっしょに学んでいきましょう。
援助職に求められる責任と義務
援助職にとって、支援現場におけるケース記録との向き合い方はとても重要です。特に、個人情報の保護と利用者や社会の安全の確保は、記録を作成する際につねに意識しておくべき基本的なポイントです。日本では平成17年に「個人情報保護法」が施行されました。今後は社会状況の変化によっては、ケース記録の重要性がこれまで以上に高まる可能性もあります。そのため、常に適切で慎重な記録作成を心がけることが求められます。
記録の内容
記録の内容・説明責任を果たす視点で、必要な情報を記録する。
ケース記録は、援助職にとって自分が提供した支援が適切な内容であったことを証明する重要な資料です。チーム支援の観点から見ると、他職種との連携や、援助職同士で対応を引き継ぐ際には、これまでの支援内容を正確に共有することが欠かせません。さらに、どのような判断に基づいて支援を行ったのか、その根拠を記録として残しておくことも重要です。
活用のヒント : 「かんたん支援記録カンタン支援計画」では、利用者さんの支援記録を、相談支援専門員さん等の他組織の支援者と共有するといった機能を使うことも可能です。限られた時間の中での情報共有がスムーズに行うことができ、効果的なチーム支援に役立ちます。
記録の内容・必要な情報に絞って記録する。
福祉現場でのケース記録は、支援の根拠となる大切な情報源です。特に緊急対応が発生した場面では、その内容をどう記録するかが重要になります。
記録が残っていれば「対応の根拠」として扱われますし、逆に記録がない場合も「意図的に記録しなかった」と受け取られることがあります。
そのため、緊急時こそ冷静に「何を記録するか」を見極め、必要な情報に絞って記録するスキルが重要となります。
活用のヒント : 「何について記録すべきか」のポイントは、各利用者様の個別支援計画に、 # ( ハッシュタグ ) をつけてキーワードとして記入しておくことで、支援記録の記入時に「計画キーワードボタン」として毎回表示されるようになります。
これにより、支援員は自然と記録すべきポイントが目に入りますので、統一した支援が行いやすくなります。
記録の内容・第三者や家族介入の記入方法に十分注意する。
もし記録の中に利用者の家族や友人などの第三者について記載がある場合、支援対象が不明確だと解釈される可能性があります。支援の専門家として、誰と支援契約を結んでいるのかを常に意識し、この視点に沿った形で記載する必要があります。
記録の内容・表現と用語選択で気をつけること
ケース記録は他者が読むことを前提とした文書であり、誰が読んでも同じように理解できる内容であることが重要です。心理的な内容についてもあいまいな表現や主観的な言い回しは避け、具体的かつ明確な記述を心がけましょう。
また、専門用語や略語の多用は記録の理解を妨げる恐れがあるため、なるべく避け、わかりやすい言葉で現象を客観的に伝えることが大切です。こうした配慮が、他の援助職や関係者による適切な支援につながります。
つまりケース記録に求められているものとは、『わかりやすく具体的な表現』『略語と専門用語を避ける』『伝えたいポイントだけを押さえた的確な表現』ということですね。
記録の信頼性・タイムリーな記録作成をする。
ケース記録は、福祉現場で援助職が行った支援を示す、唯一の証拠となる重要な記録です。しかし、記録は内容の脚色や改ざんが比較的容易であるため、信頼性を保つ工夫が求められます。その鍵のひとつが、適切なタイミングでの記録です。
たとえば、緊急対応が発生した際には、事態が収束したあと、できるだけ早く記録することが大切です。サービス提供に必要な情報を選び、要点を押さえて記録しましょう。手書きの場合、「後でまとめて」と先送りしがちですが、人の記憶は曖昧なため、時間が経つほど正確な記録は困難になります。
活用のヒント : 時間が経過して記憶が曖昧になってしまう前に、その場でスマホを利用して記録することも可能です。内容を思い出すための時間をなくし、記録作業の時間短縮にも繋がります。
記録の信頼性・専門性、記録への向き合い方、保管方法
福祉現場で援助職が記録を作成する際は、信頼性を保ち、専門性を示す文書であることが求められます。あいまいな表現や憶測を避け、「どこまでが事実か」「どこからが所見か」を明確に分けて記載することが基本です。事実に基づいた記録と、支援者としての判断や観察を丁寧に分けることで、記録の説得力が高まります。
また、記録には多くの注意点があり、時には誤って記載してしまうこともあります。そうした場合には、誤りを率直に認め、事実に基づいた簡潔かつ明確な修正を行う姿勢が大切です。誠実に記録へ向き合う態度が、記録の信頼性を高めることにつながります。
さらに、記録を適切に保管し、誰がアクセスできるかを明確に管理することも重要です。アクセス権限を定め、プライバシーと情報の保護に配慮することで、利用者との信頼関係を築き、より安心・安全な支援体制を整えることができます。
活用のヒント : 「かんたん支援記録カンタン支援計画」では支援職員の職務内容や所属サービスによって記録閲覧や記録書き込みの権限をあらかじめ決めておくことができます。(それぞれの端末のパスワード管理の重要性については言うまでもありません。)
記録の情報開示の手順を検討する。
記録に書かれている内容は利用者の情報ですが、それを文字にして記録として残した時点で、その記録は作成した支援員が所属する組織のものになります。専門職が自分の知識や経験に基づいて「どのように情報を開示するか」を決め、その方法をあらかじめ利用者に説明し、同意をもらっていれば、記録の開示を求められたときも、慌てずに対応するだけの時間的な余裕を確保できます。
メモ書き等を残す場合の注意点。
メモ書き等を残す際は、それが公式な文書として扱われる可能性があることを意識することが重要です。記録を取る際に注意すべき点は次の2つです。
1. 残したくない、あるいは残せないような情報が本当に援助活動に必要かどうか。
2. 援助職の仕事は利用者の話を覚えておくことではなく、その場での情報をもとに適切な判断を下すことだという認識を持つ。
詳細を本人が語ることによって、利用者自身の解決意識を高めることができます。
活用のヒント : スマホやタブレットの音声入力なども活用して、必要なときにタイムリーにスムーズに記録することができ、メモ書きでの伝達も減らすこともできます。
ここまで、支援者がどんな視座でケース記録を記入していくべきかということと、ケース記録に盛り込むべきポイントについて参考図書の要約をしてきました。
福祉現場での「記録の質」はそのまま「支援の質」につながるとも言えます。記録を単なる報告業務とせず、援助職としての専門性を発揮するための戦略的ツールとして活用することで、より効果的で継続的なサービス提供が可能になるかと思いますので「かんたん支援記録カンタン支援計画」を上手にご活用いただければ嬉しく思います。