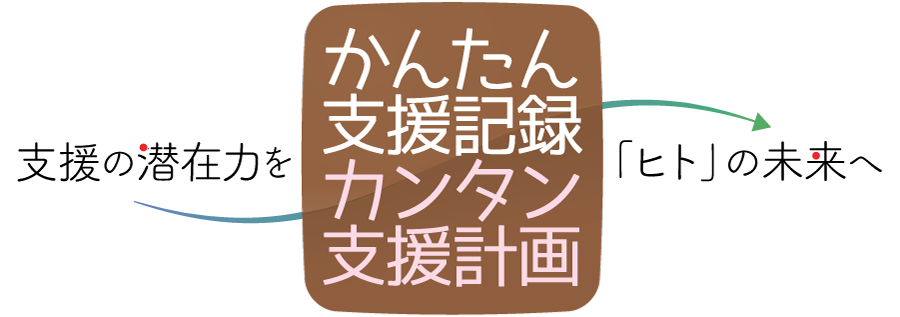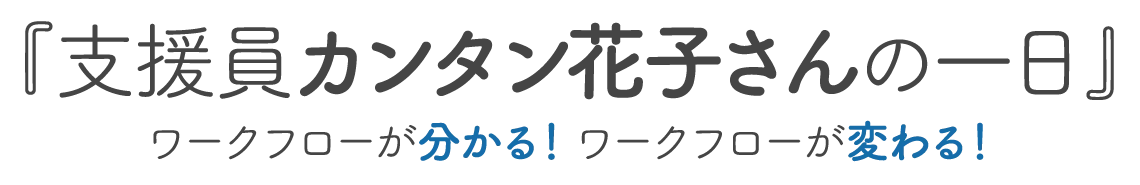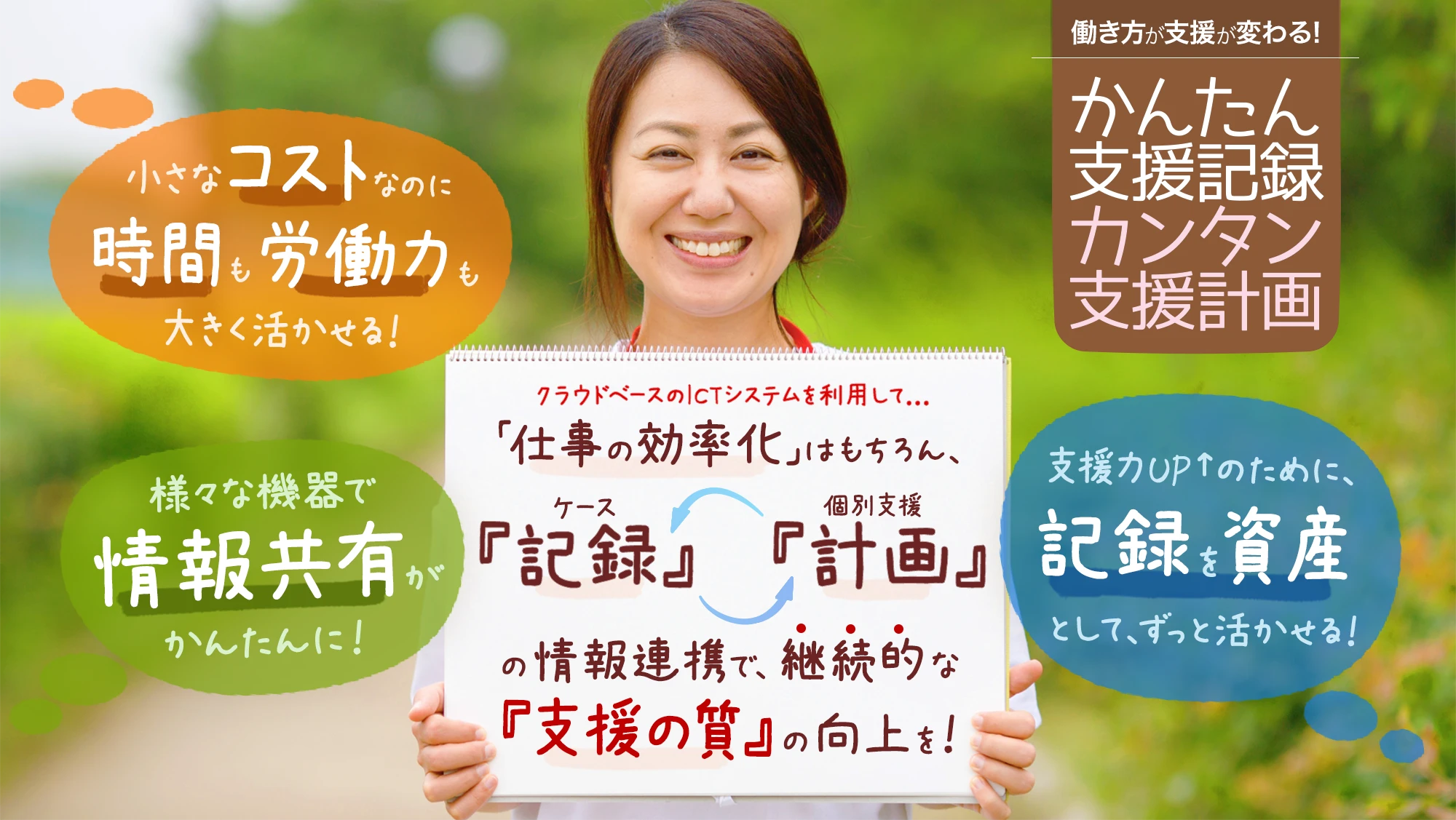活用のヒント
「かんたん支援記録カンタン支援計画」は、ニーズに応じて柔軟な使い方ができます。
こちらの「活用のヒント」をより効果的な活用のためにお役立て下さい。
情報共有について
- 個別支援計画とアセスメントシート等の帳票とを、項目を指定することで互いに自動転記することが可能です。
- レビュー : 支援記録(ケース記録)の書き方も、意識も「かんたん支援記録カンタン支援計画」によって変わりました。
- 支援記録(ケース記録・ケア記録)記入時に、個別支援計画で立てた目標を確認できると同時に、関連する記録を簡単に時系列で抽出できます。
- 特定の利用者様を指定して過去のケース記録を表示した際、その当時の個別支援計画が一緒に表示されるようになりました。
- 生活介護の場合:ケース記録(支援記録・ケア記録)をQRコードを使ってすばやくかんたんに記録できます。
- Microsoft Word / Excel を使って支援記録(ケース記録)や個別支援計画を作成すると、データの活用が難しくありませんか?
- 支援記録情報の共有が済んでいるかどうかを視覚的に確認。記録毎の既読チェックが可能になりました。
- ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その2
- レビュー : 支援記録システムで会議のペーパーレス化も。記録は活用してこそ価値がある。
- ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その5
- ケース記録だけでなく、施設外支援日報など、他の記録もハッシュタグで分類することで、いっしょに管理できます。
- 「複数サービスを利用されている利用者様」のケース記録・個別支援計画・アセスメント等をまとめて表示できるようになりました。
- 福祉事業所の人材不足・採用難を解決する一手として : ICTを活用した「ワークシェアリング」ツールとしての活用法
- 支援記録(ケース記録・ケア記録)だけでなく、会議録なども。支援員間での情報共有が、かんたんスムーズに。
- 職員以外の支援関係者に対して支援記録(ケース記録)の中から、関連する記録だけを確認できるようになりました。
- よく使うキーワードをリンクボタン(#ハッシュタグ)にして、各プロジェクト毎、記録の種類毎など、情報を束ねて状況を把握しやすく!
- レビュー : ケース記録をかんたんに共有・管理できることで、柔軟に個別支援計画がたてられるようになりました。
- グループホームでの活用 : 支援記録だけでなく、業務日報・世話人交代時の申し送りや、日中活動先との情報共有にも。小規模でも「わずかな費用」で「高い導入効果」が期待できます。
- レビュー : ケース記録のための残業が減って定時に帰宅できるように。
- レビュー : ひやりはっと・事故報告書・苦情対応 ( 支援記録に専用IDを用意して記録するケース )
- ベストプラクティス : 支援記録と個別支援計画の連携によるPDCAサイクルの構築法 : 就労継続支援B型をはじめ、それぞれの目標達成のために情報の有効活用を。
- ケース記録システムの活用で障害福祉サービスもできるだけテレワークに。新型コロナウイルス感染予防対策について。
- 「就労定着支援記録」としての使い方 : 利用者さんの支援記録(ケース記録)を相談支援員様や障害者就業・生活支援センターなどの関係者とも共有可能です。
支援記録 (ケース記録) の活用
- 個別支援計画の策定・支援経過の総括に : 生成AI ( ChatGPT API ) が支援記録を要約し、個別支援計画の目標に基づいてアドバイスを提示してくれます。
- レビュー : 支援記録(ケース記録)の書き方も、意識も「かんたん支援記録カンタン支援計画」によって変わりました。
- 支援記録 (ケース記録・ケア記録) の登録と編集 : 様々な記録手順に、効率的な記録作業フローを。
- 支援記録(ケース記録・ケア記録)記入時に、個別支援計画で立てた目標を確認できると同時に、関連する記録を簡単に時系列で抽出できます。
- 特定の利用者様を指定して過去のケース記録を表示した際、その当時の個別支援計画が一緒に表示されるようになりました。
- 生活介護の場合:ケース記録(支援記録・ケア記録)をQRコードを使ってすばやくかんたんに記録できます。
- Microsoft Word / Excel を使って支援記録(ケース記録)や個別支援計画を作成すると、データの活用が難しくありませんか?
- 福祉サービスの予定管理に : 利用者様の利用予定をまとめてチェック形式で登録。「今日の予定」を一目で確認できるようになりました。
- 支援記録情報の共有が済んでいるかどうかを視覚的に確認。記録毎の既読チェックが可能になりました。
- ケース記録(支援記録・ケア記録)記入時のテンプレートとして、端末ごとに独自のテンプレートも適用できます。
- 支援記録(ケース記録)一覧の中から、頻繁に使われている単語のリストを表示 : 単語の頻出度から傾向を把握できます。
- ケース記録(支援記録)の表示は一覧性が高く、全体像も把握しやすい!印刷もすっきり簡単!
- 支援記録(ケース記録)の「書き忘れチェック」をするための2つの方法をご紹介します。
- レビュー:個別支援計画から利用者さんの目標を、日々のケース記録の記入画面に提示できます!
- ケース記録/支援記録/個別支援計画などを音声入力する方法について。
- ケース記録(支援記録・ケア記録)をもっとすばやくかんたんに。定型文などをQRコードのスキャンだけで記録できます。また、タイムカードとしても使えます。
- 支援記録・ケース記録の内容から感情値を推測 : 注目すべき記録をすばやく見つけたり、大局的な状況を判断するための材料としてお使いいただけます。
- ケース記録だけでなく、施設外支援日報など、他の記録もハッシュタグで分類することで、いっしょに管理できます。
- 「複数サービスを利用されている利用者様」のケース記録・個別支援計画・アセスメント等をまとめて表示できるようになりました。
- 福祉事業所の人材不足・採用難を解決する一手として : ICTを活用した「ワークシェアリング」ツールとしての活用法
- 支援記録(ケース記録・ケア記録)だけでなく、会議録なども。支援員間での情報共有が、かんたんスムーズに。
- 最新の個別支援計画を簡単に確認する方法。支援記録(ケース記録・ケア記録)とともに支援の方向性を把握しておきましょう。
- 職員以外の支援関係者に対して支援記録(ケース記録)の中から、関連する記録だけを確認できるようになりました。
- よく使うキーワードをリンクボタン(#ハッシュタグ)にして、各プロジェクト毎、記録の種類毎など、情報を束ねて状況を把握しやすく!
- レビュー : ケース記録をかんたんに共有・管理できることで、柔軟に個別支援計画がたてられるようになりました。
- レビュー : ケース記録のための残業が減って定時に帰宅できるように。
- ケース記録(支援記録)の役割 : 今の時代の「ケース記録」に求められるべき要点とは?
- レビュー:ケース記録がいつでも手元で検索閲覧できます。
- レビュー : ケース記録は子供を迎えに行ってから自宅でシステムに記入し、夜勤支援員に申し送りしています。
支援記録の書き方
- レビュー : 支援記録(ケース記録)の書き方も、意識も「かんたん支援記録カンタン支援計画」によって変わりました。
- ケース記録の目的・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方ー短時間で適切な内容を表現するテクニック』その1
- ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その2
- ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その3
- ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その4
- ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その5
- ケース記録(支援記録)の役割 : 今の時代の「ケース記録」に求められるべき要点とは?
個別支援計画とアセスメントシート
- 個別支援計画とアセスメントシート等の帳票とを、項目を指定することで互いに自動転記することが可能です。
- 個別支援計画の策定・支援経過の総括に : 生成AI ( ChatGPT API ) が支援記録を要約し、個別支援計画の目標に基づいてアドバイスを提示してくれます。
- 支援記録(ケース記録・ケア記録)記入時に、個別支援計画で立てた目標を確認できると同時に、関連する記録を簡単に時系列で抽出できます。
- 特定の利用者様を指定して過去のケース記録を表示した際、その当時の個別支援計画が一緒に表示されるようになりました。
- レビュー:個別支援計画から利用者さんの目標を、日々のケース記録の記入画面に提示できます!
- ケース記録/支援記録/個別支援計画などを音声入力する方法について。
- レビュー : エクセルで個別支援計画を作ることと「かんたん支援記録カンタン支援計画」との違い。
- レビュー : 個別支援計画の確認も支援の現場ですぐに出来ます。
- 「複数サービスを利用されている利用者様」のケース記録・個別支援計画・アセスメント等をまとめて表示できるようになりました。
- 最新の個別支援計画を簡単に確認する方法。支援記録(ケース記録・ケア記録)とともに支援の方向性を把握しておきましょう。
- レビュー : ケース記録をかんたんに共有・管理できることで、柔軟に個別支援計画がたてられるようになりました。
- レビュー : ひやりはっと・事故報告書・苦情対応 ( 支援記録に専用IDを用意して記録するケース )
- 個別支援計画・アセスメント等のテンプレートに「チェック式の選択項目」が作成できるようになりました。
- ベストプラクティス : 支援記録と個別支援計画の連携によるPDCAサイクルの構築法 : 就労継続支援B型をはじめ、それぞれの目標達成のために情報の有効活用を。
「働き方」を考える
- 個別支援計画の策定・支援経過の総括に : 生成AI ( ChatGPT API ) が支援記録を要約し、個別支援計画の目標に基づいてアドバイスを提示してくれます。
- レビュー : 支援記録(ケース記録)の書き方も、意識も「かんたん支援記録カンタン支援計画」によって変わりました。
- 支援記録 (ケース記録・ケア記録) の登録と編集 : 様々な記録手順に、効率的な記録作業フローを。
- 支援記録(ケース記録・ケア記録)記入時に、個別支援計画で立てた目標を確認できると同時に、関連する記録を簡単に時系列で抽出できます。
- ケース記録の記入時にチェックした集計項目を、日別一覧表から簡単に編集できるようになりました。
- 「ケース記録アプリ」のように利用することもできます。スマートフォンはもちろん、タブレットやPCでも。
- 生活介護の場合:ケース記録(支援記録・ケア記録)をQRコードを使ってすばやくかんたんに記録できます。
- Microsoft Word / Excel を使って支援記録(ケース記録)や個別支援計画を作成すると、データの活用が難しくありませんか?
- 支援記録情報の共有が済んでいるかどうかを視覚的に確認。記録毎の既読チェックが可能になりました。
- 就労継続支援B型などに便利! 支援記録 (ケース記録) の記入時に「目標達成度を測れる数値」などを記録していくことで、日々の変化を視覚的に確認できます。
- 事業所を開業するタイミングで支援記録(ケース記録)システムを導入すれば、労力も最小限で済み、その後の運用管理もとてもスムーズになります。
- 支援記録(ケース記録)の「書き忘れチェック」をするための2つの方法をご紹介します。
- ケース記録(支援記録・ケア記録)をもっとすばやくかんたんに。定型文などをQRコードのスキャンだけで記録できます。また、タイムカードとしても使えます。
- スマートフォンを使って支援記録(ケース記録)・個別支援計画を作成する場合のメリット
- ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その2
- レビュー : 支援記録システムで会議のペーパーレス化も。記録は活用してこそ価値がある。
- 「複数サービスを利用されている利用者様」のケース記録・個別支援計画・アセスメント等をまとめて表示できるようになりました。
- 福祉事業所の人材不足・採用難を解決する一手として : ICTを活用した「ワークシェアリング」ツールとしての活用法
- 支援記録(ケース記録・ケア記録)だけでなく、会議録なども。支援員間での情報共有が、かんたんスムーズに。
- 職員以外の支援関係者に対して支援記録(ケース記録)の中から、関連する記録だけを確認できるようになりました。
- レビュー : ケース記録をかんたんに共有・管理できることで、柔軟に個別支援計画がたてられるようになりました。
- グループホームでの活用 : 支援記録だけでなく、業務日報・世話人交代時の申し送りや、日中活動先との情報共有にも。小規模でも「わずかな費用」で「高い導入効果」が期待できます。
- レビュー : ケース記録のための残業が減って定時に帰宅できるように。
- ケース記録(支援記録)の役割 : 今の時代の「ケース記録」に求められるべき要点とは?
- レビュー : ひやりはっと・事故報告書・苦情対応 ( 支援記録に専用IDを用意して記録するケース )
- ベストプラクティス : 支援記録と個別支援計画の連携によるPDCAサイクルの構築法 : 就労継続支援B型をはじめ、それぞれの目標達成のために情報の有効活用を。
- ケース記録システムの活用で障害福祉サービスもできるだけテレワークに。新型コロナウイルス感染予防対策について。
- レビュー : ケース記録は子供を迎えに行ってから自宅でシステムに記入し、夜勤支援員に申し送りしています。
- 「就労定着支援記録」としての使い方 : 利用者さんの支援記録(ケース記録)を相談支援員様や障害者就業・生活支援センターなどの関係者とも共有可能です。
「活用のヒント」の全記事
- 支援記録 (ケース記録) 、支援計画、出欠情報のCSVデータダウンロードにも対応。
- 個別支援計画とアセスメントシート等の帳票とを、項目を指定することで互いに自動転記することが可能です。
- 個別支援計画の策定・支援経過の総括に : 生成AI ( ChatGPT API ) が支援記録を要約し、個別支援計画の目標に基づいてアドバイスを提示してくれます。
- レビュー : 支援記録(ケース記録)の書き方も、意識も「かんたん支援記録カンタン支援計画」によって変わりました。
- 支援記録 (ケース記録・ケア記録) の登録と編集 : 様々な記録手順に、効率的な記録作業フローを。
- 支援記録(ケース記録・ケア記録)記入時に、個別支援計画で立てた目標を確認できると同時に、関連する記録を簡単に時系列で抽出できます。
- ケース記録の記入時にチェックした集計項目を、日別一覧表から簡単に編集できるようになりました。
- 特定の利用者様を指定して過去のケース記録を表示した際、その当時の個別支援計画が一緒に表示されるようになりました。
- 「ケース記録アプリ」のように利用することもできます。スマートフォンはもちろん、タブレットやPCでも。
- 生活介護の場合:ケース記録(支援記録・ケア記録)をQRコードを使ってすばやくかんたんに記録できます。
- ケース記録の目的・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方ー短時間で適切な内容を表現するテクニック』その1
- Microsoft Word / Excel を使って支援記録(ケース記録)や個別支援計画を作成すると、データの活用が難しくありませんか?
- 福祉サービスの予定管理に : 利用者様の利用予定をまとめてチェック形式で登録。「今日の予定」を一目で確認できるようになりました。
- 新型コロナウイルス対策 : 利用者様の平均体温推移をグラフで確認することで、感染症蔓延の兆候を把握しやすくなります。
- 支援記録情報の共有が済んでいるかどうかを視覚的に確認。記録毎の既読チェックが可能になりました。
- ケース記録(支援記録・ケア記録)記入時のテンプレートとして、端末ごとに独自のテンプレートも適用できます。
- 支援記録(ケース記録)一覧の中から、頻繁に使われている単語のリストを表示 : 単語の頻出度から傾向を把握できます。
- ケース記録(支援記録)の表示は一覧性が高く、全体像も把握しやすい!印刷もすっきり簡単!
- 就労継続支援B型などに便利! 支援記録 (ケース記録) の記入時に「目標達成度を測れる数値」などを記録していくことで、日々の変化を視覚的に確認できます。
- 事業所を開業するタイミングで支援記録(ケース記録)システムを導入すれば、労力も最小限で済み、その後の運用管理もとてもスムーズになります。
- 支援記録(ケース記録)の「書き忘れチェック」をするための2つの方法をご紹介します。
- レビュー:個別支援計画から利用者さんの目標を、日々のケース記録の記入画面に提示できます!
- ケース記録/支援記録/個別支援計画などを音声入力する方法について。
- ケース記録(支援記録・ケア記録)をもっとすばやくかんたんに。定型文などをQRコードのスキャンだけで記録できます。また、タイムカードとしても使えます。
- カスタマイズ事例 : 使い方や運用方針に応じて柔軟にカスタマイズできます。
- スマートフォンを使って支援記録(ケース記録)・個別支援計画を作成する場合のメリット
- ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その2
- レビュー : 支援記録システムで会議のペーパーレス化も。記録は活用してこそ価値がある。
- レビュー : エクセルで個別支援計画を作ることと「かんたん支援記録カンタン支援計画」との違い。
- ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その3
- 支援記録・ケース記録の内容から感情値を推測 : 注目すべき記録をすばやく見つけたり、大局的な状況を判断するための材料としてお使いいただけます。
- レビュー : 個別支援計画の確認も支援の現場ですぐに出来ます。
- ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その4
- ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その5
- ケース記録だけでなく、施設外支援日報など、他の記録もハッシュタグで分類することで、いっしょに管理できます。
- 「複数サービスを利用されている利用者様」のケース記録・個別支援計画・アセスメント等をまとめて表示できるようになりました。
- 福祉事業所の人材不足・採用難を解決する一手として : ICTを活用した「ワークシェアリング」ツールとしての活用法
- 支援記録(ケース記録・ケア記録)だけでなく、会議録なども。支援員間での情報共有が、かんたんスムーズに。
- 最新の個別支援計画を簡単に確認する方法。支援記録(ケース記録・ケア記録)とともに支援の方向性を把握しておきましょう。
- 職員以外の支援関係者に対して支援記録(ケース記録)の中から、関連する記録だけを確認できるようになりました。
- よく使うキーワードをリンクボタン(#ハッシュタグ)にして、各プロジェクト毎、記録の種類毎など、情報を束ねて状況を把握しやすく!
- レビュー : ケース記録をかんたんに共有・管理できることで、柔軟に個別支援計画がたてられるようになりました。
- グループホームでの活用 : 支援記録だけでなく、業務日報・世話人交代時の申し送りや、日中活動先との情報共有にも。小規模でも「わずかな費用」で「高い導入効果」が期待できます。
- レビュー : ケース記録のための残業が減って定時に帰宅できるように。
- ケース記録(支援記録)の役割 : 今の時代の「ケース記録」に求められるべき要点とは?
- レビュー : ひやりはっと・事故報告書・苦情対応 ( 支援記録に専用IDを用意して記録するケース )
- 個別支援計画・アセスメント等のテンプレートに「チェック式の選択項目」が作成できるようになりました。
- ベストプラクティス : 支援記録と個別支援計画の連携によるPDCAサイクルの構築法 : 就労継続支援B型をはじめ、それぞれの目標達成のために情報の有効活用を。
- 支援記録(ケース記録)・個別支援計画・アセスメント等、ぞれぞれの使い方に応じてカスタマイズも可能です。
- ケース記録システムの活用で障害福祉サービスもできるだけテレワークに。新型コロナウイルス感染予防対策について。
- レビュー:ケース記録がいつでも手元で検索閲覧できます。
- レビュー : ケース記録は子供を迎えに行ってから自宅でシステムに記入し、夜勤支援員に申し送りしています。
- 「就労定着支援記録」としての使い方 : 利用者さんの支援記録(ケース記録)を相談支援員様や障害者就業・生活支援センターなどの関係者とも共有可能です。