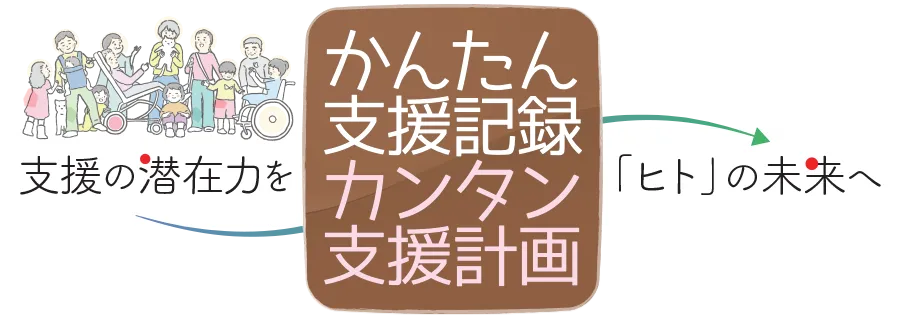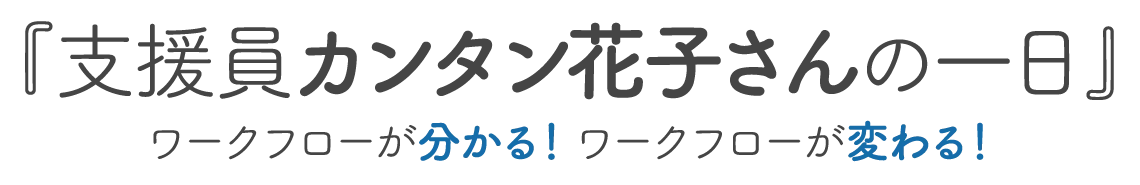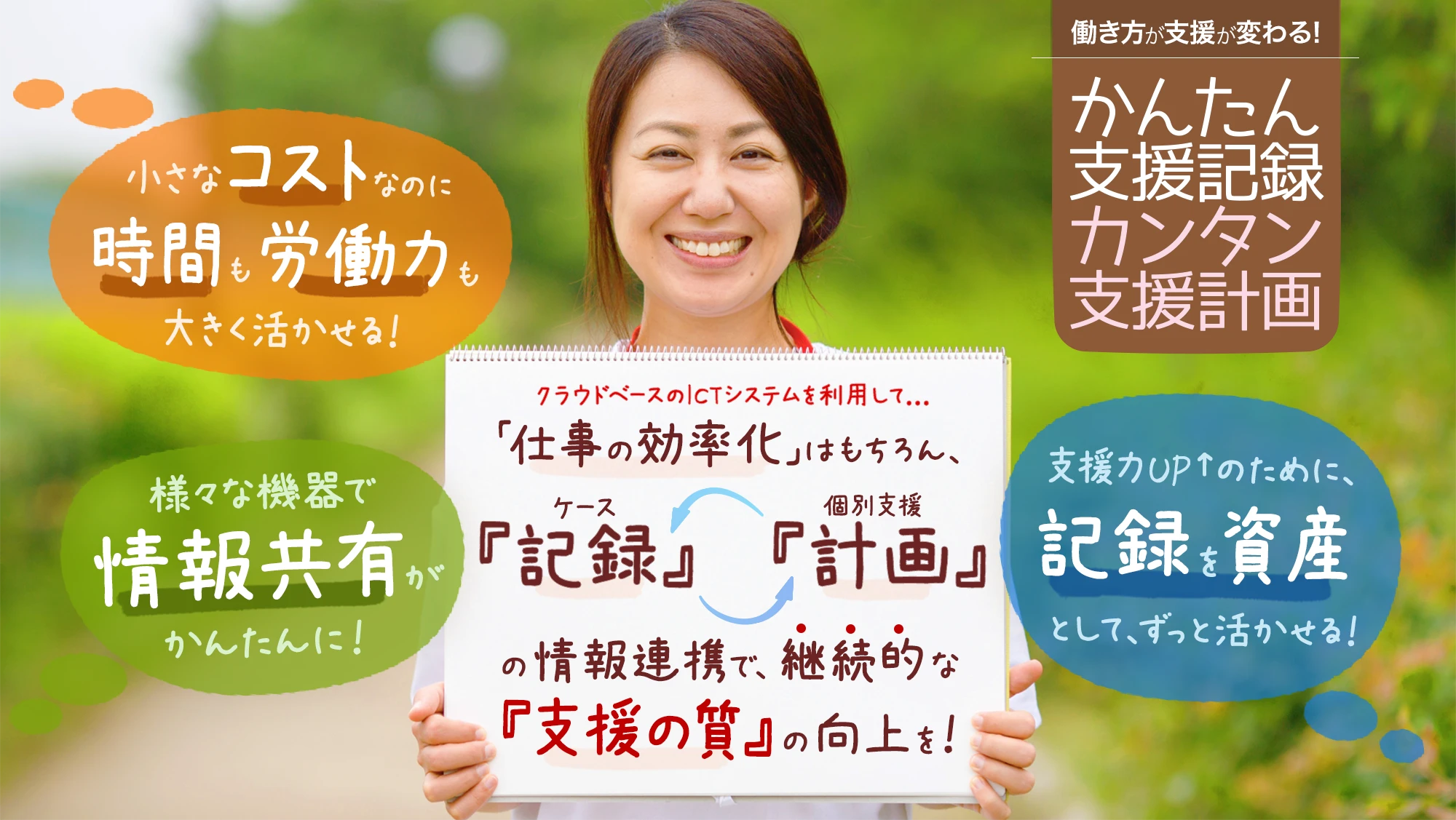ケース記録の書き方・参考図書紹介『相談援助職の記録の書き方‐短時間で適切な内容を表現するテクニック』その5

システムを導入して記録を「資産」として活かすには、支援員が利用者さんの情報を正確かつ効果的に記録していく必要があります。こうした土台が整うと、福祉サービスの本来の価値を持続的に高めることへとつながります。そのためには、どのような視点でケース記録を書いていくことが重要なのでしょうか。
まず、印象はとても主観的なものであり、他者と共有することが難しいという点に注意が必要です。そこで、感じたことだけを書くのではなく、その印象を持った理由となる客観的な事実をはっきり示し、「印象の根拠」を分かる形で記録することが大切です。
このための枠組みとして有効なのが、メンタルステータスエグザム(MSE)です。MSEは、利用者の心理的状態を客観的に評価し、記録するための標準的な手法であり、主観に偏りがちな印象の記録を、より信頼性の高いものにするのに役立ちます。
活用のヒント :
『個別支援計画』と『ケース記録( ≒ 支援記録・サービス提供記録・経過記録 )』で、状態を表すキーワードにハッシュタグ (#独語 #暴言など) を設定しておくと、情報共有だけでなくハッシュタグを付けたキーワードの頻出度合いの確認も出来ますので、利用者様の状態の把握がしやすくなります。
メンタルステータスエグザム=MSE(Mental Status Exam)を使って情報を可視化する。
MSE(メンタルステータスエグザム)は、日本語で「精神状態の査定」と訳され、医師が面接時に利用者の心理的・精神的状態を観察・質問を通じて記述する手法です。日本の福祉・医療現場でも、他職種との情報共有やチーム支援に役立つ「現象の捉え方」として活用されています。MSEは、利用者本人の主観的データと、援助者による客観的観察データの両方を基にしています。評価項目は13項目で、これに慣れることで、面接中に「どこを観察すべきか」「何に着目すべきか」など、必要な観察ポイントを意識的に捉えられるようになり、支援の質を向上させることができます。
活用のヒント : 「かんたん支援記録カンタン支援計画」では、テンプレートの登録がかんたんにできますので、ポイントとなる項目をあらかじめテンプレートにしておくと、ポイントにそって面談・支援記録記入をすすめることができます。
MSEの13の項目について
- 外見、身だしなみ
利用者の服装、身だしなみ、衛生状態を観察します。これにより、精神的な状態や生活環境が反映されることがあります。 - 行動・運動機能
利用者の動きや態度を評価します。過度に落ち着きがない、逆に異常に静か、などの異常行動に注意を払います。姿勢、身振り手振り、歩き方なども含まれます。 - 話し方
話すスピード、流暢さ、声のトーンなどを観察します。早口、遅い、途切れがちなど、言語的な異常がないか確認します。本人のコミュニケーションのパターンにも注意します。 - 思考過程
発言の内容やなめらかさはどうなのか、利用者が話すそれぞれの内容がどのように関連しているか、仮に理屈が通っていても話の展開はどうなのか、といったことに注目します。 - 思考の内容
思考の内容を検討することで、さまざまな状況をアセスメントすることができます。しかし、気分障害の症状であったり、薬の使用や身体疾患が原因であったりすることもあるのでその点にも注意します。 - 知覚障害
利用者が幻覚(視覚、聴覚など)を体験しているかどうかを評価します。幻聴や幻視がある場合は、精神的な異常を示唆することがあります。 - 面接時の態度
面接時に支援者に対してどのような態度を取っているか観察すると、さまざまな情報を収集することができます。態度を表す用語を実際の記録に残す際には、用語選択には十分な注意が必要となります。 - 感覚/意識と見当識
本人の意識が覚醒しているか、清明か、また時間、場所、人物、状況を正しく認識しているのかを見ます。 - 利用者の報告による気分
利用者の全般的な「気分」を知ることで、さまざまな精神障害の可能性が検討できます。 - 援助者の観察による感情・情緒の内容と振幅
利用者が訴える気分と、援助職が受け取る情報が一致しているかどうかに注意を払います。また、利用者の訴えと、援助職の客観的情報は分けることが有用です。また、感情・情緒を観察する際には、その内容だけでなく、気分の波にも注意を払う必要があります。 - 知能
知的能力の詳細な判定は心理職による検査となりますが、援助職とのやり取りにおいて年齢的なものを加味した上で、通常にやり取りできるレベルであるかどうかを見ます。 - 洞察力
洞察力とは利用者自身が問題や状況に対して、その原因や意味を理解する能力があるかを指します。 - 判断力
MSEにおける判断力とは、自分の言動が与える影響を検討し、自身の衝動や情緒を制御する力のことです。成長する中でいろいろな経験を経ながら習得していくものでもあるので、洞察力、判断力はともに年齢に見合った機能レベルであるかを見極めることが重要です。
活用のヒント : 「かんたん支援記録カンタン支援計画」では、利用者様の特定の様子の出現度合いなどを「感覚」ではなく「数値」として記録し、グラフにできますので、日々の変化を視覚的に確認することも可能です。
今回は、目の前の利用者の状態を言語化し、他者と情報を共有するための視点として、MSEを要約しました。
ここで挙げたポイントは、「かんたん支援記録カンタン支援計画」のテンプレートやハッシュタグ、グラフなどの機能を活用することで、複数の支援員でも要点を押さえたケース記録を無理なく記入でき、日々の支援にも役立てることができます。ぜひご活用ください。