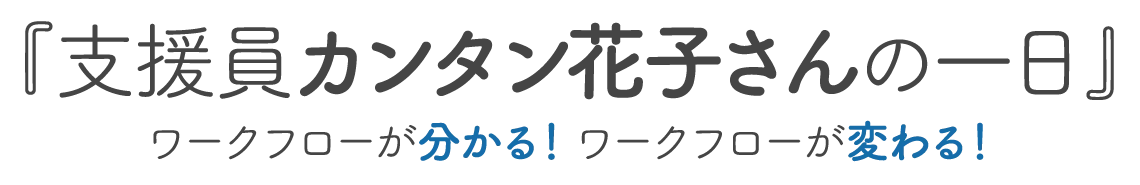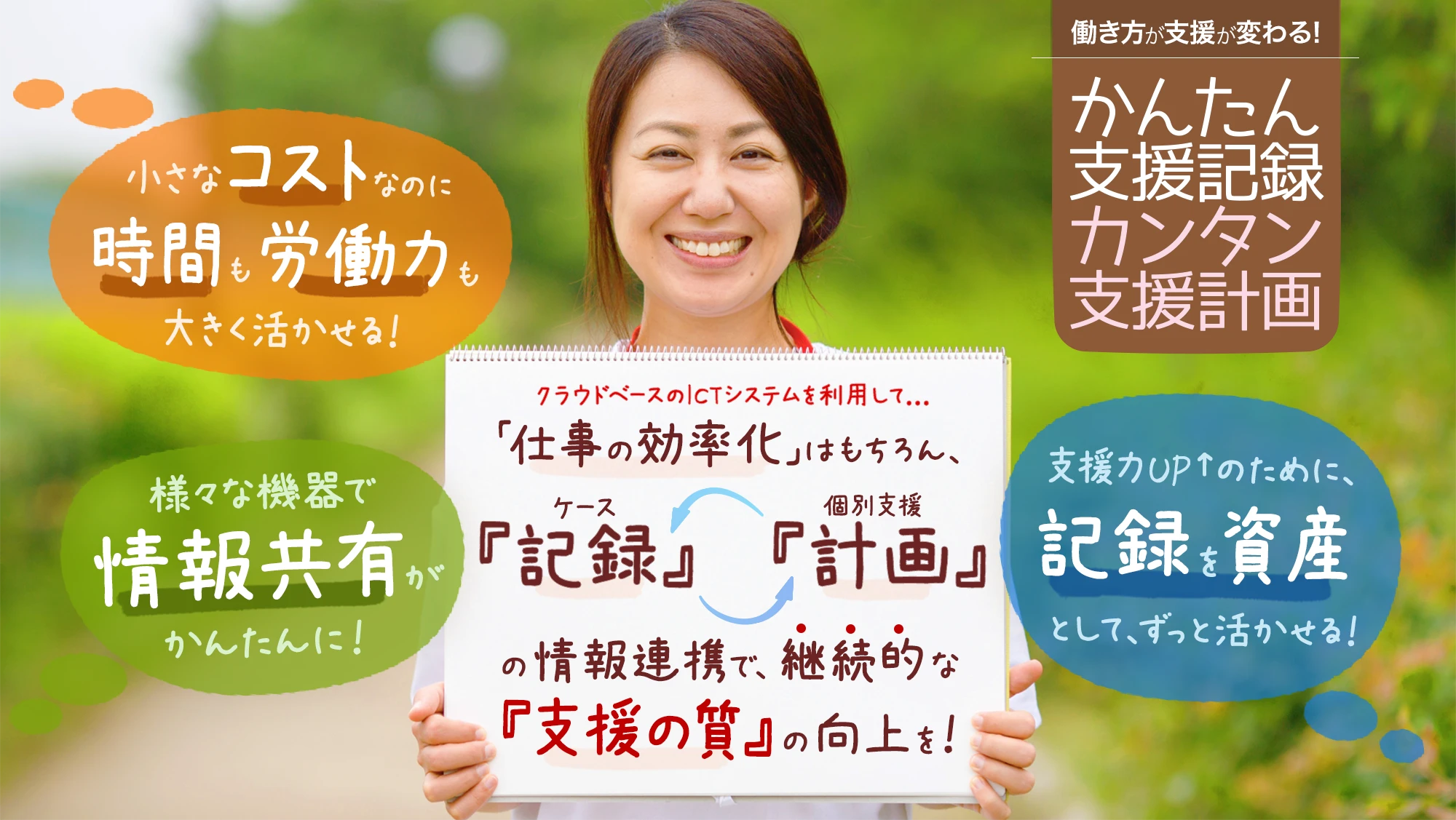記事リスト : ケース記録の書き方
ここでは、ケース記録を記入する際に参考となる情報を一覧しています。
「かんたん支援記録カンタン支援計画」を使うと、記録記入の効率化だけでなく、自然に統一支援ができ、様々な情報を支援に活用していくための土台として利用できますが、より上手な「記録の書き方」を理解することで、さらなる相乗効果が生まれ、より大きな「支援のチカラ」となってくれるはずです。
「記録は大事だと分かってはいても、日々の業務に追われてつい後回しに…」
「支援員によって記録のポイントが違い、支援の方向性がブレてしまう…」
障害福祉の現場で、このようなジレンマを抱えていませんか?
ケース記録は、支援の質に直結する重要な業務です。 それは単なる報告書ではなく、自分の支援を客観的に振り返り、思考を整理し、専門性を高めるためのプロセスそのものです。
この記事では、ケース記録が持つ本来の役割を改めて見つめ直し、日々の記録業務を「義務的な作業」から「支援の質を高める戦略的ツール」へと変えるための視点と、それを実現する具体的な方法をご紹介します。
TIPS : 「記録情報の活用」に難しさを感じてしまう「一番の原因」。それは自然に活用できる「環境を経験したことがない」から、ではありませんか? 「環境」があれば活用の仕方は後からでもついてきます。
続きを読む
「毎日の記録業務に追われて、支援に集中する時間がない…」
「支援員によって記録の質がバラバラで、カンファレンスでの情報共有がうまくいかない…」
「せっかく書いた記録が、次の支援に活かされている実感が持てない…」
障害福祉の現場で、このような悩みを抱えていませんか?
日々のケース記録は、利用者一人ひとりに質の高い支援を届けるための土台となる、いわば「未来への資産」です。しかし、その重要性を理解していても、多忙な業務の中で記録を効果的に活用できていないのが現実かもしれません。
この課題を解決する鍵は、支援員の「主観的な印象」を、チームで共有できる「客観的な事実」へと変換することにあります。 そのための強力な枠組みが、今回ご紹介する「メンタルステータスエグザム(MSE)」です。
続きを読む
日々の支援に追われ、「記録を書く時間があるなら、もっと利用者様と関わりたい」と感じることはありませんか? 「とりあえず何をしたか書いておけばいい」… そう思ってしまう瞬間があるかもしれません。
しかし、支援記録(ケース記録)の本質は、単なる報告書や監査のための書類ではありません。それは、利用者様の人生の軌跡を繋ぎ、私たち支援者の専門性を証明し、チームを不測の事態から守る「最強の資産」です。
今、なぜ多忙な中でこそ「丁寧な記録」が求められるのか。その本質的な理由を4つの視点で紐解きます。
続きを読む
記録を記入する際には、明快な文章をひと思いに素早く書けることが理想的ではありますが、時間がなかったり、経験が不足していたり、パソコンによる入力が苦手だったり、と何らかのハードルを感じてしまう状況はあります。
そんなハードルを乗り越えるべく、支援記録記入ページにて、内容欄に記入されたテキストを ボタン一つで、記録の書き方の基本をおさえた「記録調の文体(叙述形式)」として、簡潔にまとめる機能を追加いたしました。
ボタン一つで、記録の書き方の基本をおさえた「記録調の文体(叙述形式)」として、簡潔にまとめる機能を追加いたしました。
さらに、設定されているテンプレートに沿って内容をまとめてフォーマットされますので、共有する上での「読みやすさ」や「一貫性」にも貢献してくれると思います。
テキストを「内容欄」に書き終えた後、1. 気になる部分を選択して ボタンを押した場合には、その選択部分のみを、2. 特に選択せずに
ボタンを押した場合には、その選択部分のみを、2. 特に選択せずに ボタンを押した場合には、内容全体を校正し、まとめてくれます。
ボタンを押した場合には、内容全体を校正し、まとめてくれます。
続きを読む
お知らせ : 弊社では F-SOAIP開発者である、埼玉県立大学 嶌末憲子教授 / 国際医療福祉大学大学院 小嶋章吾特任教授 のお二人と共に、当システムを通じた障害福祉領域でのF-SOAIP効果検証を予定しております。ご興味をお持ちの方は、お問い合わせ頂くか、ご試用お申し込み時にご連絡下さい。
ご存知の方も多いと思いますが、F-SOAIP は現代の代表的なケース記録( ≒ 支援記録・サービス提供記録・経過記録 )の記録手法のひとつです。 基礎となる枠組みは、記録フォーマットとして、「 F = 焦点・主題 」ごとに「 S = 利用者の主観情報 、 O = 支援者等の客観情報 、 A = 支援者の判断や解釈 、 I = 支援者による介入・実施内容 、P = 以降の支援での予定 」の各項目に分解・分類して記述していく、という点です。
続きを読む
システムを導入して記録を「資産」として活かすには、支援員が利用者さんの情報を正確かつ効果的に記録していく必要があります。こうした土台が整うと、福祉サービスの本来の価値を持続的に高めることへとつながります。そのためには、どのような視点でケース記録を書いていくことが重要なのでしょうか。
まず、印象はとても主観的なものであり、他者と共有することが難しいという点に注意が必要です。そこで、感じたことだけを書くのではなく、その印象を持った理由となる客観的な事実をはっきり示し、「印象の根拠」を分かる形で記録することが大切です。
このための枠組みとして有効なのが、メンタルステータスエグザム(MSE)です。MSEは、利用者の心理的状態を客観的に評価し、記録するための標準的な手法であり、主観に偏りがちな印象の記録を、より信頼性の高いものにするのに役立ちます。
活用のヒント :
『個別支援計画』と『ケース記録( ≒ 支援記録・サービス提供記録・経過記録 )』で、状態を表すキーワードにハッシュタグ (#独語 #暴言など) を設定しておくと、情報共有だけでなくハッシュタグを付けたキーワードの頻出度合いの確認も出来ますので、利用者様の状態の把握がしやすくなります。
続きを読む
記録というものは、援助職の業務を体系的にとらえるうえで極めて有効なツールであるわけですが、記録に必要とされる項目をあらかじめテンプレートにして登録しておくことで、支援の習熟度によらずに明確に記録を作成することができます。
続きを読む
前回は、援助職がケース記録を書く際に意識すべき視点と、記録に盛り込むべき基本的なポイントについて整理しました。
「記録は大事だし、書かなければいけない」と分かってはいても、つい後回しになってしまう…。そんな経験をお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、ケース記録の作成は支援の質にも直結する大切な作業です。ケース記録を記入すること自体が、自分の考えを整理し、客観的に振り返るためのプロセスでもあります。
ケース記録の役割が明確になると、「何を記録すべきか」が見えてきます。すると、記録を意識した支援ができるようになり、結果として日々の業務時間の使い方にも変化が生まれてくるはずです。
本記事では、ケース記録を通じてどのように専門性を可視化し、他職種との連携や説明責任にどう活かせるのかを掘り下げていきます。
続きを読む
福祉現場における記録の本質は、単なる業務の報告ではなく「支援の質を向上させるための資産となる」点にあります。この貴重なデータを最大限に引き出し、効率的かつ低コストで活用可能な基盤として整備できるのが、クラウド型記録システム「かんたん支援記録カンタン支援計画」です。
しかし、どれだけ優れたシステムが整っていても、「どのように書くべきか」という記録に盛り込むべき重要な要素を理解していなければ、現場で本当の意味で活かすことはできません。
前回は、『相談援助職の記録の書き方―短時間で適切な内容を表現するテクニック』という書籍を参考に、ケース記録( ≒ 支援記録・サービス提供記録・経過記録 )の目的や、記録の歴史的背景について要約しました。
今回はその続きとして、現場の支援者がどのような視点でケース記録を記入するべきかについての具体的な記載ポイントを分かりやすく紹介していきます。
続きを読む
日々、支援者の皆さんはケース記録を書く際に、どの観点で、どのように記述すべきかを考え、工夫を凝らしていることと思います。そこで、ここでは「ケース記録の書き方」の重要なポイントを押さえていきたいと思います。
参考にさせていただく本は、『相談援助職の記録の書き方―短時間で適切な内容を表現するテクニック』です。本書は、アメリカのカリフォルニア州で10年以上の経験を持つソーシャルワーカー、ケースワーカーである八木亜紀子さんによって執筆されました。八木さんは福島県立医科大学の特任准教授で、精神保健福祉士および公認心理師としても活躍しています。
ケース記録の書き方を正しく理解し、現場での支援力を向上させるためのポイントを押さえていきましょう。
続きを読む
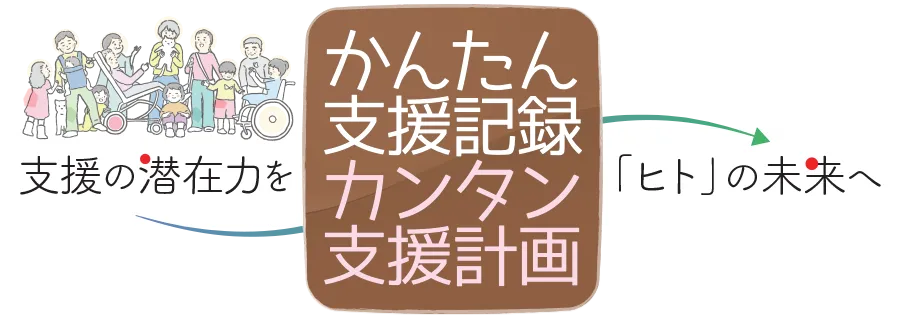
 ボタン一つで、記録の書き方の基本をおさえた「記録調の文体(叙述形式)」として、簡潔にまとめる機能を追加いたしました。
ボタン一つで、記録の書き方の基本をおさえた「記録調の文体(叙述形式)」として、簡潔にまとめる機能を追加いたしました。